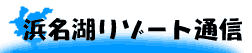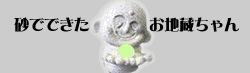|
 伝統的漁法 伝統的漁法
浜名湖は十五日ごとに海水が入れ替わる。満月と新月の大潮のとき,外海から魚とプランクトンが流れ込み,豊穣の湖となる。豊富な栄養と日の光が,浜名湖に
あふれる。干満の差を利用して海苔が育つ。海苔は,引き潮のとき湖面に顔を出して光合成をする。カキも潮の満ち引きによって美味しさをます。
浜名湖の名産といえばうなぎ。その稚魚をメッコという。春先、浜名湖へ満ち潮にのってやって来る。体色がしろいのでしらすうなぎともいう。それをすくって
きて養殖業者に売る。養殖もののうなぎが幅を利かせるなかで、天然ものは珍重される。うなぎつぼという竹筒を沈めておいて、夜中に入ったのを朝早くとりに
いく。今は竹でなくプラスチックになったが,目印の浮きがぷかぷかと波間に浮かんでいるのが見える。
三ケ日に住む徳さんは、天秤棒にたらいを担いで,うなぎを信州まで売りにいった。三ケ日から別
所街道を通って,飯田まで生きたまま運ぶのは大変だった。途中の水場で、うなぎに水浴びをさせて生気を取り戻した。国道一五一号線はうな
ぎ街道といってもよかった。今は昔、行商が行き来したころの話だ。
佐久目の大野武雄さんはずっと浜名湖で漁をしていた。早春、春告げ魚のサヨリが,水面
に浮かぶように細身の体をひらめかす。底引き網でサヨリを獲った日々が忘れられない。
「あのころはよう獲れた。八束も獲った日があった。一束が一〇キロ,全部で八十キロだよ」。青緑の肌を輝かせてはねる。サヨリは糸づくり
にして,煎り酒にポンズをたらして食べると美味しい。
 大野さんは浜名湖の伝統漁法はすべてこなす。シダの束(柴ソダ)を湖に沈めて芝エビを獲った。網で獲るよりエビが傷まないから高く売れる。船で流した角目網
漁もやった。角立て網は,湖面に立てた杭に網を掛けておく。日没から夜明けにかけて、網に沿って魚が内側に入ってくる。琵琶湖の?漁(えりりょう)のような
ものだ。網の先は袋になっていて,ハゼ、クルマエビ、コチ、サヨリなどが獲れた。 大野さんは浜名湖の伝統漁法はすべてこなす。シダの束(柴ソダ)を湖に沈めて芝エビを獲った。網で獲るよりエビが傷まないから高く売れる。船で流した角目網
漁もやった。角立て網は,湖面に立てた杭に網を掛けておく。日没から夜明けにかけて、網に沿って魚が内側に入ってくる。琵琶湖の?漁(えりりょう)のような
ものだ。網の先は袋になっていて,ハゼ、クルマエビ、コチ、サヨリなどが獲れた。
ボラが水面をバシャと跳ねると,周りをぐるりと打たせ網で囲んでしまう。
「網といっても袋になっているのじゃあない。テニスのネットみたいなものだ。網に
重しをつけて張るから,潜らんように浮きをつける昔は,浮き玉じゃあなく桶だったよ」。網に入っているボラを、湖面
を棹でたたいて追い込む。周囲に張りめぐらされたよしずの上にぴょんぴょんとボラが跳び上がる。それをタモですく
う。ボラたたきと地元の人はいう。
夜は夜で,灯りを照らしてドウマン(甲丸ガニ)をすくいにいった。浜名湖にし
か生息しないこのカニは、前脚のはさみが見るからに大きく、棒切れなどひき千切ってしまう。秋ともなると身のつまったドウマンが獲れる。その味は香港ガニ
よりおいしい。今では庄内半島あたりでしか獲れない。量も年々減少して、もはや幻のカニとなりつつある。
東岸の雄踏では、昔から焚き夜漁がおこなわれていた。月のない夜、かがり火を焚いて底にいるコチやカニ、ヒラメをサデで突いた。伝統的な焚き夜漁も、最近
は多分に観光化して、集魚灯のような灯りを照らして漁をするようになった。
アサリは業者が大きなカクワでとる。水面から長い筒メガネでのぞくと、貝の目がみえる。アサリの水管が並んでいるのだ。それをカクワでさらいとる。水面
が胸までしかないように見えるが、実際はもっと深い。鉄の一本歯の下駄をはいて いるからだ。高さが一メートルくらいのもある。小さい貝はふるい落とし、大粒のだけをチャカ船に積む。大きさによって一箱(二十二キロ)五千円から九千円
で取引される。八十三歳になる源さんは、日の出とともに作業を始め、午前中で仕舞う。もっとやってもいいが、無理はしないことにしている。それでも五箱く
らいは獲る。
 入出という漁師町、江戸時代から地先網漁がみとめられていた。さらに浜名湖北部に勢力をのばしていく。今では当時ほどの活気は見られないが、ここの佃煮は
美味しい。古い家並みがつづく狭い路地から女が現れてきた。日焼けした顔つきが、暮らしてきた歳月を物語る。浜名湖の潮風に磨かれて,風景の中にとけこん
でいる。最近、浜名湖に注ぐ都田川にダムが出来たために、川の水が減って汽水湖の水が
濃くなったという。そのためかタイやサバ、タコなどが獲れるようになった。一方で豊富だった稚魚が育たなくなり、湖面
漁業に大きな問題を投げかけている。外海からの流れも、以前ほどではなくなった。事実、去年(二〇〇三)は赤潮が発
生し、アサリに大打撃を与えた。 入出という漁師町、江戸時代から地先網漁がみとめられていた。さらに浜名湖北部に勢力をのばしていく。今では当時ほどの活気は見られないが、ここの佃煮は
美味しい。古い家並みがつづく狭い路地から女が現れてきた。日焼けした顔つきが、暮らしてきた歳月を物語る。浜名湖の潮風に磨かれて,風景の中にとけこん
でいる。最近、浜名湖に注ぐ都田川にダムが出来たために、川の水が減って汽水湖の水が
濃くなったという。そのためかタイやサバ、タコなどが獲れるようになった。一方で豊富だった稚魚が育たなくなり、湖面
漁業に大きな問題を投げかけている。外海からの流れも、以前ほどではなくなった。事実、去年(二〇〇三)は赤潮が発
生し、アサリに大打撃を与えた。
|